「第三種冷凍機械責任者と第二種電気工事士のダブル受験って無謀ですか?」
この時期になると上記の質問を頂くことが多く、今年も同様の質問が来ましたので今回は記事にしてみました。
.png)
上記はマシュマロで頂いた質問です。同様の悩みをお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください!
先に結論「電工二種と冷凍機械責任者の同年受験はOK!」
先に結論から話しますと、第二種電気工事士と冷凍機械責任者の同年受験は十分に現実的な挑戦です。
それぞれの資格に必要な勉強時間は、電工二種が学科・技能合計で100時間、第三種冷凍機械責任者が70時間程度です。
それぞれの試験日ですが、電工二種の学科が9~10月の間、技能が12月の中旬、冷凍機械責任者が11月9日なので、よほど仕事が忙しいという人でもな全く無謀ではありませんい限り、この勉強時間を捻出することは難しくないはずです。
つまり、やる気と、ちょっとした計画性さえあれば、十分に両方合格は狙えます。
 ヘタ・レイ
ヘタ・レイちなみに同年受験は珍しいことではなく、毎年多くの方が挑戦して合格していますよ!
いきなり冷凍2種や冷凍1種もあり
冷凍機械責任者には第3種から第1種まであることはご存知だと思いますが、今から勉強するのであれば上位の第2種や第1種を狙ってもよいと思います。
冷凍機にはとくに受験資格も無いですし、最終的に2種や1種を狙っているのであれば、最初から上位資格を取得するのは無駄が無く効率的です。
もちろん3種と比べて内容は難しくなりますが、「最初から高みを目指す」という選択は、最短ルートでゴールにたどり着きたい方にはむしろ理にかなっています。
私自身も第3種を飛ばして第2種をいきなり受験していますので、この方法はまったく無謀ではありません!
ちなみに、第2種で150時間、第1種で200~300時間程度の勉強が必要です。第1種だと電工二種と合わせて400時間の勉強が必要になるので、仕事やプライベートが忙しく、あまり勉強時間が取れない方は、無理せず下位の資格を受けてくださいね。
【令和7年度版】電工二種と3冷を同年受験する人への実践アドバイス
ここまで読んでみて、「電工二種と冷凍機械責任者を同年受験する」と決めた方へ勉強方法などのアドバイスがあります。
どちらも絶対に合格したいという方は必ず見てください!
令和7年度の試験日程
同年受験は無謀ではないのですが、1個の資格を受験するより大変なのは間違いないため、スケジュール管理が大切です。
まずは、今年度の試験日程などを確認していきましょう!
第二種電気工事士
- 申込期間
8月18日~9月4日 - 学科試験(筆記かCBTを選択)
筆記:10月26日
CBT:9月19日~10月6日 - 技能試験
12月13日又は12月14日 - 受験料
9,300円(電子申請)、9,600円(郵送申請)
冷凍機械責任者
- 申込期間
8月18日~9月3日 - 試験日
11月9日 - 受験料
第三種:9,800円(電子申請)、10,300円(書面申請)
第二種:11,100円(電子申請)、11,600円(書面申請)
第一種:17,300円(電子申請)、17,800円(書面申請)



受験料はどちらも高額です。
会社が受験料を負担してくれるなら良いですが、自腹で受験する人は絶対に合格したいですよね。
勉強スケジュール「電工の筆記は〇〇〇で受験がオススメ!」
次におすすめの勉強スケジュールを紹介します。
それぞれの受験日を日程順に並べますと、以下のようになります。
| 電工二種(学科) | 冷凍機械責任者 | 電工二種(技能) | |
| CBT:9月19日~10月6日 | 筆記:10月26日 | 11月9日 | 12月13日or14日 |
基本的に日程が直近の試験を優先して勉強するほうが効率が良いため、まずは電工二種の学科から学習しましょう。
ここで大切なのは電工二種をCBTで受験することです。もし筆記で受験してしまうと冷凍機械責任者の試験日まで2週間程度しか猶予がありません。
もちろん電工二種と冷凍機械責任者を並行して勉強すれば、実際に取れる冷凍機械責任者の勉強時間はもっと多くなりますが、並行して勉強するやり方は効率が落ちやすいので避けた方が無難です。



学習する内容が似たような資格なら並行して勉強しても良いのですが、電工と冷凍機は勉強内容が全く被ってないんですよね・・・。
というわけで、電工二種の学科はCBT試験の一発目である9月19日に受験することが最も効率的です。
これなら、今から電工二種の学科の勉強を開始すれば、9月19日まで1か月半以上期間がありますので、電工二種学科の合格に必要な勉強時間は余裕で確保できます。
電工二種の学科が終わったあと、すぐに冷凍機械責任者の勉強を開始すれば、11月9日の試験日まで1か月以上の勉強時間が取れます。
そして電工二種の技能の勉強は、冷凍機械責任者の試験が終わってから始めればこちらも1か月半以上ありますので、合格に必要な勉強時間は余裕で確保できています。
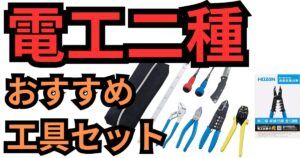
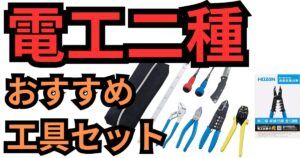
いかがでしょうか。こうやって見ると、電工二種と冷凍機械責任者の同年受験はスケジュール的には全くきつくないことがわかって頂けたと思います。
なお、冷凍機を上位の第1種や第2種で受験する場合は、電工二種の学科と並行して今から勉強していきましょう。とはいえ、試験日が近い電工二種の配分を多めにしてください。
冷凍機械責任者と第二種電気工事士を取得するメリット
このブログを見ている方の多くは、冷凍機械責任者や第二種電気工事士がビルメンにとって重要な資格だということをご存じかと思います。
ただ、改めてそのメリットを整理しておくことで、「これから目指してみようかな」と思えるきっかけになるかもしれません。
転職・就職で有利になる
まず最大のメリットは、やはり就職・転職の際に圧倒的に有利になることです。
特に第二種電気工事士は、ビルメン業界において「持っていて当たり前」とすら言われるほどの基本資格であり、求人票に「必須」と書かれていることも少なくありません。
また、「実務経験がなければ意味がない」といった声を聞くこともありますが、それは資格を持っている人が言える話です。資格を持っていない時点で、応募すらできない会社があるのも事実です。
つまり、「スタートラインに立つため」にも、これらの資格は持っておくべきなのです。
さらに資格を持っていれば、職場での信用や評価にもつながります。現場で何も資格がないと肩身が狭く感じることもありますが、有資格者であれば「この人はある程度知識がある」と見てもらえるため、自信にもつながります。
資格手当がもらえる
ビルメンの世界では、資格手当がそのまま給料アップに直結します。
たとえば、ある現場では以下のような資格手当が支給されています。
- 第二種電気工事士:月2,000円
- 第三種冷凍機械責任者:月2,000円
つまり、両方持っていれば、毎月4,000円の手当がつく可能性があるのです。年間で考えると48,000円。ちょっとした旅行に行ける金額ですね。
資格手当は、取得さえしてしまえば毎月自動的にもらえる「不労所得」です。仕事の内容が変わらなくても収入が増える、これほど嬉しい話はありません。
また、第二種冷凍機械責任者では4,000円、第一種冷凍機械責任者では6,000円程度の手当が支給される会社もあります。上位資格を目指す動機にもなりますね。
※他の資格手当については、以下の記事にまとめてあります。
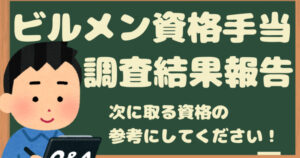
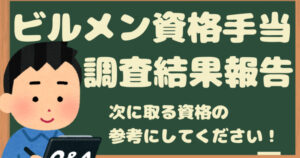
他資格を受験する際に有利になる場合がある
第二種電気工事士と冷凍機械責任者は、他の資格を取得するときに有利に働くことがありますので一部を紹介します。
- 第二種電気工事士
- 各種冷凍機械責任者
- 第1種冷媒フロン類取扱技術者→詳しくはこちら
- 第二種以上の冷凍機械責任者
- ビル管理士の講習に必要な実務経験の短縮→詳しくはこちら
- 第一種冷凍機械責任者
- ビル管理士の講習に必要な実務経験の短縮→詳しくはこちら
- 社会保険労務士の受験資格(ビルメンとは関係無いですが)
このように様々な資格に影響があります。ビルメンだと、認定電気工事従事者の受講や消防設備士の科目免除に利用している人が多いですね。
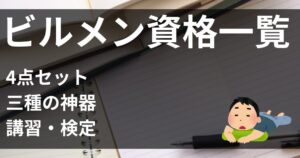
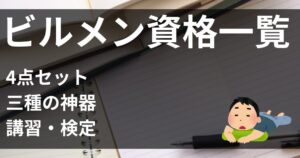
まとめ「同年受験するなら今から勉強を始めよう」
冷凍機械責任者と第二種電気工事士は、どちらもビルメンにとって非常に価値のある資格です。同じ年に2つの資格を取得するのは簡単ではありませんが、不可能ではありません。むしろ、今このブログを読んでいるあなたなら、十分に狙えるはずです。
試験日までのスケジュールを逆算すれば、今から少しずつ勉強を始めることで、無理なく合格レベルまで到達できます。とくに初学者の方は「どこから手を付ければいいのか分からない」と悩みがちですが、安心してください。私のブログでは、それぞれの資格におすすめの教材や勉強法も紹介していますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。
どちらの資格も取得すれば、就職・転職活動でのアピール材料になり、資格手当や昇給につながるケースもあります。同年ダブル合格は、努力した分だけしっかりリターンがある挑戦です。
少しでも「やってみようかな」と思ったなら、まずは教材選びから始めてみてください。同年受験するなら今すぐ勉強開始です!
第二種電気工事士の勉強におすすめの記事
冷凍機械責任者の勉強におすすめの記事



YouTubeリスナーの方におすすめの教材のアンケートを取っていますので、こちらも参考にしてみてください。
【関連記事】ビルメン4点セットおすすめ教材アンケート


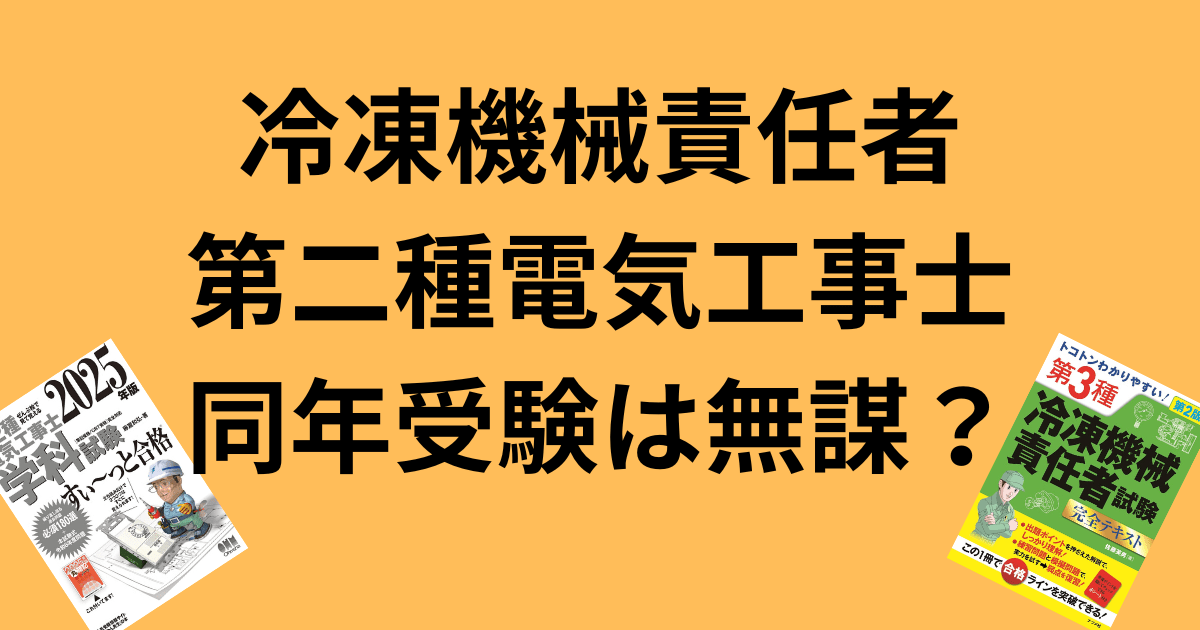

コメント